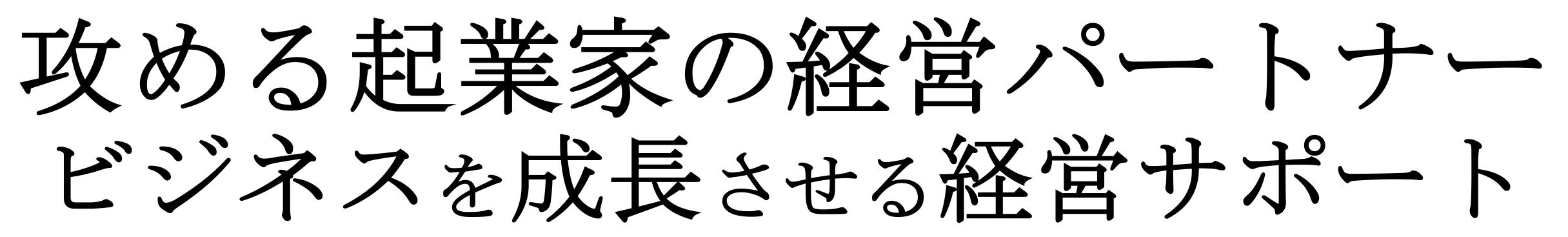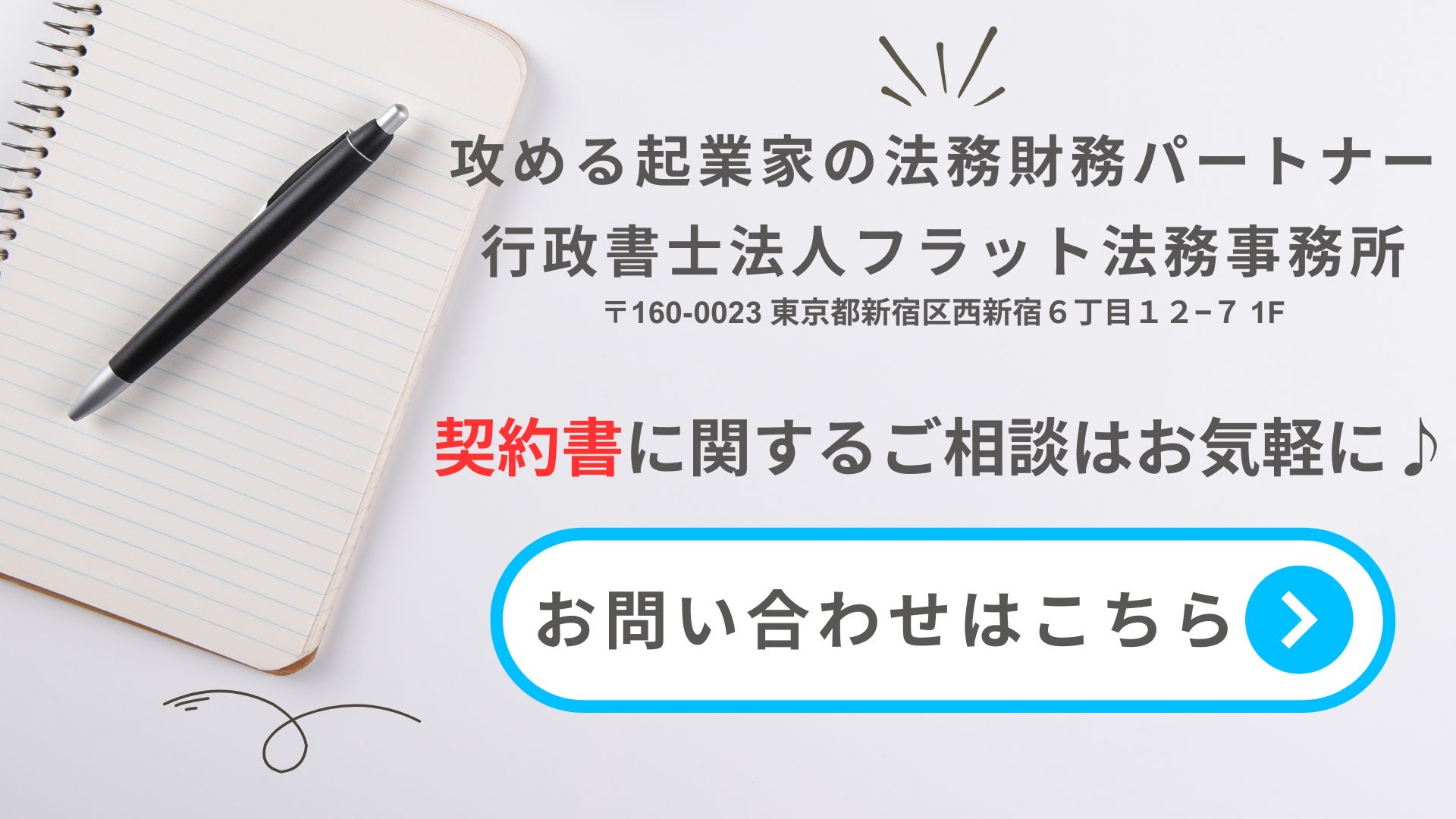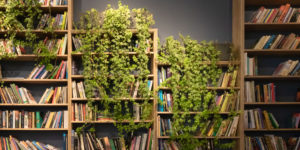経営権譲渡契約書と事業譲渡契約書の違いを徹底解説!

企業の売却や事業譲渡は、経営戦略の一環として重要な局面であることが多いです。この際に必要となる契約書として「経営権譲渡契約書」と「事業譲渡契約書」がありますが、それぞれの役割や目的には違いがあります。本記事では、これら2つの契約書の違いを詳しく解説し、スムーズな譲渡手続きを進めるためのポイントを紹介します。そして、実務における具体的な事例や注意点を交えながら、経営者や担当者が押さえておくべき事項を徹底的に掘り下げます。

1. 経営権譲渡契約書と事業譲渡契約書の基本的な違い
1.1.経営権譲渡契約書とは?
経営権譲渡契約書は、会社の支配権、すなわち経営権の譲渡に関する契約書です。主に株式譲渡を通じて経営権を移転する場合に使用され、会社そのものの所有権が移動します。会社の経営者が変わるため、会社全体の方針や運営に大きな影響を与えることが多いです。
- 株式譲渡: 経営権譲渡契約の多くは株式の譲渡によって行われます。譲渡する株式が過半数を超える場合、事実上の経営支配権が新しい株主に移行することとなります。
- 企業の継続性: 経営権譲渡の場合、会社は同じ法人格を維持し、契約や債務もそのまま引き継がれます。
1.2.事業譲渡契約書とは?
事業譲渡契約書は、会社の特定の事業を他の企業や個人に譲渡する際に作成される契約書です。これは、会社そのものが譲渡されるわけではなく、特定の事業のみが切り出されて移転される点が特徴です。
- 事業の一部譲渡: 事業譲渡契約では、譲渡対象が事業そのものであり、資産や負債、取引先との契約など、譲渡範囲が契約によって詳細に決められます。
- 法人の独立性: 事業譲渡後も譲渡元の会社は存続し、譲渡先の企業がその事業を新たに運営することになります。
2. 経営権譲渡契約書のポイント
経営権譲渡契約書を作成する際には、特に株式譲渡に関わる事項が中心となります。以下に、実務上で押さえておくべきポイントを挙げます。
2.1.株式譲渡の範囲と方法
契約書の中で、譲渡する株式の範囲や株価評価が明確に定められていないと、後にトラブルの原因となります。特に、株価評価方法については、複数の手法が存在するため、予め双方の合意を得ることが重要です。
事例:株価評価のずれによるトラブル ある中小企業の経営権譲渡において、株価評価方法に対する認識の違いから、譲渡後に譲渡金額に関する紛争が発生しました。譲渡者が企業価値を市場ベースで評価したのに対し、譲受者は簿価ベースで評価しており、その結果、大きな差額が生じたのです。このケースでは、最終的に再評価の合意を取り付けましたが、契約書の時点で評価基準を明確にしておけば、こうした問題は避けられたでしょう。
2.2.経営権の移転時期
経営権の移転タイミングについても契約書で明確に規定する必要があります。特に、大規模企業や公開企業の場合、移転の手続きが複雑になることがあります。また、株主総会の承認や、関係機関への届出が必要となる場合もあるため、法的な手続きが遅延することも考慮し、移転時期を慎重に設定します。
2.3.従業員の処遇
経営権譲渡によって、従業員の雇用関係がどのように影響を受けるかも契約書で取り決めることが重要です。さらに、新しい経営陣の方針によって雇用条件が変わる可能性があるため、事前に従業員との話し合いを行い、適切な対応を取ることが求められます。
3. 事業譲渡契約書のポイント
事業譲渡契約書には、事業の範囲や譲渡対象となる資産の詳細が含まれます。具体的には、事業譲渡に伴う法的な手続きや税務上の取り扱い、契約移転に関する注意点などを理解しておくことが必要です。
3.1.譲渡範囲の特定
事業譲渡契約書では、譲渡する事業の範囲を明確に定める必要があります。資産、負債、顧客リスト、知的財産、雇用契約など、どの範囲が譲渡対象となるのかを契約書に記載することで、後の紛争を防ぎます。
事例:知的財産の譲渡を巡るトラブル あるソフトウェア開発会社が事業譲渡を行った際、譲渡対象に含まれる知的財産の権利移転に関してトラブルが発生しました。譲渡契約書において知的財産の詳細が曖昧だったため、譲渡先が使用できる範囲について後から紛争となり、契約の見直しが必要になったのです。事前に知的財産権の範囲や利用条件を明確にしていれば、このような問題は防げたでしょう。
3.2.取引先との契約の引き継ぎ
事業譲渡後、取引先との契約が自動的に引き継がれるわけではありません。取引先の同意が必要となるケースも多いため、事前に取引先との交渉を進め、同意を取り付ける手続きが重要です。また、取引先が譲渡に反対した場合の対応策も事前に検討しておくべきです。
3.3.税務上の影響
事業譲渡に伴う税務処理も重要なポイントです。譲渡所得税や消費税など、譲渡に伴う税務上の取り扱いについては、専門家(税務は税理士です)と協力して慎重に進める必要があります。
4. スムーズな譲渡手続きを進めるためのポイント
経営権譲渡や事業譲渡をスムーズに進めるための具体的なポイントをいくつか紹介します。
4.1. 事前準備を徹底する
契約締結前のデューデリジェンス(適正評価)を行い、譲渡対象の企業や事業の財務状況、法的リスクを徹底的に洗い出します。
4.2. 弁護士や専門家の協力を得る
譲渡契約は複雑な法的要素が絡むため、専門家を早い段階で関与させ、適切なアドバイスを受けることが重要です。
4.3. 双方の合意を明確にする
契約書において、双方の合意事項を具体的かつ明確に記載することで、後のトラブルを防ぐことができます。特に、譲渡範囲や株価評価など、争点となりやすい事項は詳細に取り決めるべきです。
5.店舗等の運営権を譲渡する場合について
店舗などの運営権を譲渡する場合も、経営権や事業譲渡と似た手続きが必要ですが、いくつか特有の注意点があります。具体的には、店舗の物件や顧客リスト、雇用関係、取引先との契約など、店舗運営に必要なリソースをどのように譲渡するかが重要なポイントとなります。ここでは、店舗運営権の譲渡に関する具体的な要点を解説します。
5.1. 店舗運営権の譲渡とは?
店舗運営権の譲渡は、ある企業や個人が運営している店舗やフランチャイズの権利を他の企業や個人に譲渡することを指します。この場合、主に以下の要素が譲渡対象となります。
- 物件の賃貸借契約: 店舗の物件を賃借している場合、その賃貸借契約が譲渡対象に含まれることがあります。オーナーの同意が必要な場合も多く、事前に交渉が必要です。
- 営業権(のれん): その店舗が築いてきた顧客基盤やブランド力、信用を引き継ぐ「のれん代」も譲渡の一部となる場合があります。
- 在庫や設備: 店舗内の在庫や設備、什器備品も譲渡の対象になることが一般的です。
- 従業員の引き継ぎ: 店舗に所属する従業員の雇用関係がどうなるかも重要な検討事項です。事前に従業員と譲渡条件について合意を取る必要があります。
5.2. 店舗運営権譲渡における契約のポイント
店舗運営権を譲渡する場合、契約書には事業譲渡契約書や賃貸借契約書の内容に加え、店舗運営に特化した条項を盛り込む必要があります。
5.2.1物件賃貸借契約の引き継ぎ
店舗が賃貸物件で運営されている場合、賃貸借契約の名義を譲渡先に変更する手続きが必要です。多くの場合、物件オーナーの同意が必要であり、オーナーが譲渡に反対した場合、店舗運営に支障が生じることがあります。
事例:オーナーの同意を得られず譲渡が困難に ある飲食チェーン店が経営不振に陥り、複数の店舗を他社に譲渡しようとしましたが、物件オーナーが新たな借主に不信感を抱き、賃貸借契約の名義変更に同意しなかったため、店舗譲渡が進まなかったというケースがありました。このような場合、物件オーナーとの事前交渉が非常に重要です。
5.2.2営業権(のれん)の評価
店舗のブランドや顧客基盤に基づく「営業権(のれん)」の価値は、譲渡契約において重要な要素です。店舗が長年にわたり築いてきた信頼やブランド力は、事業譲渡の一部として高く評価される場合があります。その評価方法についても契約書で明確にしておく必要があります。
事例:営業権評価に対する見解の違い ある美容院チェーンがフランチャイズ店舗の譲渡を行った際、譲渡元と譲渡先で営業権(のれん)評価に関する意見が食い違い、最終的に独立した評価機関を介して評価を行いました。このように、第三者の評価を導入することが、トラブル回避につながることがあります。
5.2.3在庫や設備の譲渡
店舗内に存在する在庫や設備も、譲渡契約に含まれることが一般的です。これらの物品の譲渡価格をどのように算定するかは、店舗運営の状況に応じて異なります。特に在庫品については、古い在庫や売れ残り品がどのように評価されるかが問題となることが多いため、詳細な取り決めが必要です。
5.2.4従業員の処遇
店舗に勤務する従業員の雇用は、譲渡後も維持するのか、それとも解雇するのかを事前に決定し、契約書に明記することが重要です。労働法に基づく適切な対応が求められ、特に譲渡先が雇用条件を変更する場合は、従業員との協議が必要です。
5.3. 店舗運営権譲渡の際に気を付けるべき法的リスク
5.3.1賃貸借契約に基づく制限
店舗の賃貸借契約には、名義変更や賃借人の地位承継に関する制限が含まれている場合があります。契約内容をよく確認し、オーナーから必要な同意を得ることが不可欠です。これを怠ると、契約違反となり、物件からの退去を命じられる可能性もあります。
5.3.2取引先との契約
店舗運営に関連する取引先との契約(仕入れ業者、物流業者など)の引き継ぎも重要な課題です。これらの契約は自動的に譲渡されるわけではないため、譲渡先企業が同じ条件で契約を引き継げるかどうかを事前に確認し、取引先の同意を取り付ける必要があります。
5.4. 店舗運営権譲渡の成功事例と失敗事例
成功事例:スムーズな店舗譲渡での業績向上 ある飲食チェーン店は、複数の店舗を業績の良い新興企業に譲渡する際、譲渡元の店舗運営マニュアルや従業員をそのまま引き継ぐ形でスムーズな譲渡を実現しました。この結果、譲渡後も顧客基盤が維持され、新オーナーは短期間で業績を向上させることができました。譲渡に際して、物件オーナーや従業員との円滑なコミュニケーションが成功の鍵となりました。
失敗事例:契約内容の不備によるトラブル ある小売店の譲渡では、在庫品や什器の状態に関する取り決めが不十分だったため、譲渡後に譲受者が古い在庫品の廃棄処分に多額の費用を要し、想定外の損失を被る結果となりました。このケースでは、譲渡前の在庫や設備の状態をしっかり確認し、契約書に明記しておけばトラブルを防ぐことができたでしょう。
6.まとめ
経営権譲渡契約書と事業譲渡契約書にはそれぞれ異なる特徴があり、どちらの方法を選ぶかは、譲渡の目的や対象によって異なります。特に、店舗運営権の譲渡に関しては、物件や顧客基盤、従業員の処遇に関する特有の注意点があります。また、スムーズな譲渡手続きを進めるためには、事前準備を徹底し、専門家の協力を得て、契約書に詳細な取り決めを記載することが必要です。
*記事内の事例(ケース)については、行政書士法人フラット法務事務所で経験したものだけでなく想定ケースも含まれ、実際の事例とは異なることがあります。また、関係法令は記載した時点のものです。
企業法務や財務等の経営に関することや
契約書の作成やチェックのご相談はお気軽に行政書士法人フラット法務事務所までお問い合わせください♪
行政書士法人フラット法務事務所は、積極的に事業展開している起業家・経営者の皆様に、事業に専念し利益の追求できるようにサポートさせていただき、共にお客様の事業利益の最大化を目指します。
実際にベンチャー企業や中小企業で経営を経験してきたからこそ提案できる企業法務、財務、新規事業の法的調査、融資、出資、経営管理部門サポート等をさせていただきます。個人事業主、一人会社、小さな企業の方もご遠慮なくご相談ください。
公式HP
契約書サポート(契約書作成代行、リーガルチェック)
経営管理サポート(バックオフィスを総合的にサポート)
法務財務サポート