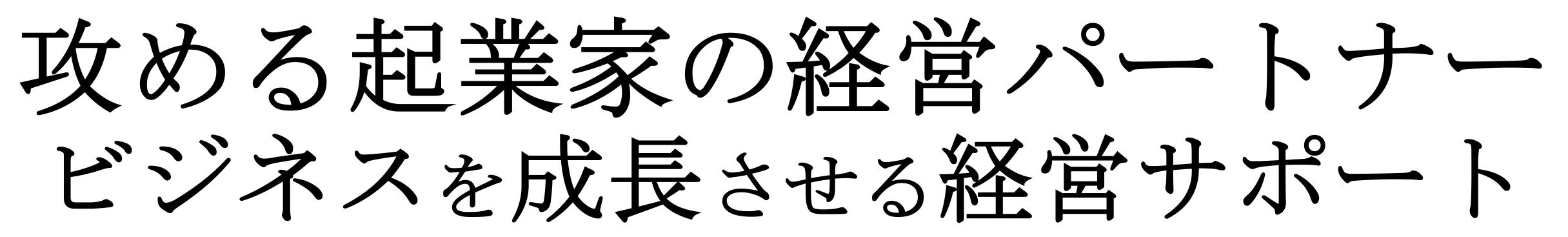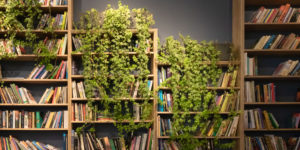不動産売買契約書・重要事項説明書の作成実務とリスク回避策!宅建士で行政書士が解説

はじめに
不動産取引は、契約実務の中でも特に大きな契約行為のひとつです。マイホーム購入、投資用不動産の取得、事業用地の売買など、取引金額は数千万円から数億円に及ぶことも珍しくありません。そのため、不動産売買契約書や重要事項説明書の内容に不備があると、後のトラブルは甚大です。
本記事では、宅地建物取引士(宅建士)であり、契約書作成の専門家である行政書士の立場から、不動産売買契約書・重要事項説明書の実務とリスク回避策について、事例を交えて解説します。

1. 不動産売買契約書と重要事項説明書の役割
1-1 不動産売買契約書とは
不動産売買契約書は、売主と買主の間で取り交わす「権利義務を明文化した合意文書」です。代金額、支払方法、引渡し日、所有権移転登記、違約金などが規定されます。
1-2 重要事項説明書とは
重要事項説明書は、宅建業法に基づき、宅建士が契約締結前に買主へ説明しなければならない法定書面です。物件の権利関係、法令制限、インフラ整備状況、管理規約など、専門知識がないと理解が難しい内容を事前に可視化する役割を担います。
1-3 両者の違いと関係性
- 売買契約書 → 売主と買主の「合意内容」を示す
- 重要事項説明書 → 契約の「前提条件」を説明する
実務では、重要事項説明書で不動産の状況を正確に把握した上で、売買契約書に落とし込む流れとなります。
2. 実務でよくあるトラブル事例
2-1 境界未確定トラブル
ある土地取引で「境界が未確定」のまま契約を進めた事例がありました。買主は後に隣地所有者と境界を巡って紛争となり、測量費用や訴訟費用を負担せざるを得ませんでした。本来であれば、重要事項説明書や売買契約書で「境界確定済みか否か」を確認し、合意の上での取り決めとして「境界確定は売主(or買主)負担で行う」などと定める必要があります。
2-2 ローン特約の不備
住宅ローンを利用する買主にとって「融資特約(ローン特約)」は命綱です。しかし、契約書で「ローン不成立の場合は契約解除できる」としか記載がなく、返還期限や手続方法が明確でなかったため、手付金返還を巡る紛争が発生しました。ローン特約条項は、実務で最も慎重に作成すべき部分です。一般的には白紙解約とすることが多いです。
2-3 瑕疵担保責任(契約不適合責任)の扱い
旧法下では「瑕疵担保責任」とされていた規定は、2020年の民法改正で「契約不適合責任」となりました。もし雨漏りやシロアリ被害が後日発覚した場合、契約書に責任範囲や期間を明確に定めていなければ、損害賠償や契約解除のリスクが高まります。
3. 売買契約書に盛り込むべき主要条項
契約書作成の現場では、以下の条項を特に慎重にチェックする必要があります。(なお、法定の項目もありますが、今回は考慮していません)
- 売買代金・支払方法・手付金の性質(解約手付か否か)
- 引渡日・所有権移転登記の時期
- ローン特約の具体的条件(融資額・金融機関・期限)
- 契約不適合責任(責任期間・免責の有無)
- 違約金・損害賠償額の予定
- 付帯設備表・物件状況報告書の添付
- 反社会的勢力の排除条項
実務では、特に「手付解除の期限」「契約不適合責任の存続期間」などは曖昧にしてしまうと、後の紛争に直結する可能性が高まります。
4. 重要事項説明書でのチェックポイント
重要事項説明書は、宅建士が記名押印の上で説明する法定書面です。次の内容が特に重要です。(なお、法定の項目もありますが、今回は考慮していません)
- 登記記録に関する事項(所有権、抵当権など)
- 都市計画法・建築基準法による制限(用途地域、建ぺい率、容積率)
- 私道負担の有無
- 電気・ガス・水道・下水道の整備状況
- マンションの場合:管理規約・修繕積立金・管理費
- 土壌汚染・地盤沈下など環境リスク
特に、マンション取引では「管理費や修繕積立金の滞納状況」を説明せず、買主が多額の債務を負ってしまうケースが考えられます。これは宅建士の説明義務違反に直結します。
5. 行政書士・宅建士が実務で助言するリスク回避策
5-1 ダブルチェック体制
契約書は売主・買主双方に利害があるため、宅建士による説明はもちろんのこと行政書士による契約書チェックを入れるという二重体制が望ましいです。
5-2 曖昧な表現を避ける
「概ね良好」「後日協議する」などの曖昧な文言は、後日の解釈トラブルを生みます。具体的な数値や期限を明記することが肝要です。
5-3 取引スキームに応じた特約条項
- 投資用不動産 → 賃貸借契約の承継条項
- 農地取引 → 農地法の許可取得条件
- 法人取引 → 反社会的勢力排除条項や税務条項
契約目的に応じて柔軟に特約を設けることで、リスクを大幅に軽減できます。
6. 実務コメント:現場での注意点
- 契約直前に「重要事項説明が形式的になっている」ケースを多く見ます。買主が十分理解していないまま署名押印することは危険です。
- 契約書は仲介業者が用意する雛形をベースに作成されることが多いため、買主側は不利な条項がないか慎重にチェックした方が安全です。
- 契約不適合責任については「引渡し後3か月以内」など短期で限定されることが多いため、買主は実際の利用を想定して交渉することが重要です。
7. 行政書士がチェックするメリット
不動産取引において宅建士は重要事項説明を担いますが、第三者が入ることで、契約書自体の法的な完成度を担保することも重要です。そこで、行政書士が契約書をチェックすることで次のようなメリットがあります。
7-1 法律的観点からのリスク分析
行政書士は契約法・民法等の関連法規に精通しており、条項ごとの法的リスクを事前に洗い出すことができます。例えば、曖昧な「特約条項」や、民法改正に対応していない「旧来の文言」など、実務では見落とされがちな部分を指摘可能です。
7-2 中立的立場での契約調整
用意された雛形をそのまま用いると、買主に不利な条項が含まれるケースがあることも十分にありえます。行政書士は中立的な立場から、双方にとって公平な契約内容となるよう契約書の確認を行い、将来の紛争を未然に防ぎます。
7-3 実務に即したカスタマイズ
投資用不動産、法人間取引、相続案件など、取引の形態によって必要な条項は大きく異なります。行政書士が契約書をチェックをすることで、取引の実情に合わせた契約書へカスタマイズすることが可能です。
7-4 紛争予防・万一の対応策提示
契約書を精査する段階で、将来的に起こり得る紛争パターンを想定し、予防策を条項化できます。また、万一紛争が発生しても、契約書が適切であれば解決までの時間や費用を大幅に軽減できます。
8.まとめ
不動産売買契約書と重要事項説明書は、不動産取引における両輪であり、片方でも不備があれば重大なトラブルを招きます。境界問題、ローン特約、契約不適合責任など、典型的なリスクは条項や説明を工夫することで予防可能です。
宅建士が重要事項を作成・説明し、行政書士が契約書を精査することで、安心かつ公正な取引を実現できます。
不動産取引を検討している方や、業務で契約書作成に関わる方は、ぜひ専門家のサポートを活用し、リスクを最小化した取引を心がけてください。
*記事内の事例(ケース)については、行政書士法人フラット法務事務所で経験したものだけでなく想定ケースも含まれ、実際の事例とは異なることがあります。また、関係法令は記載した時点のものです。
企業法務や財務等の経営に関することや契約書の作成やチェックのご相談はお気軽に行政書士法人フラット法務事務所までお問い合わせください♪
不動産法務サポート
https://flat-office.com/realestate/
行政書士法人フラット法務事務所は、積極的に事業展開している起業家・経営者の皆様に、事業に専念し利益の追求できるようにサポートさせていただき、共にお客様の事業利益の最大化を目指します。
実際にベンチャー企業や中小企業で経営を経験してきたからこそ提案できる企業法務、財務、新規事業の法的調査、融資、出資、経営管理部門サポート等をさせていただきます。個人事業主、一人会社、小さな企業の方もご遠慮なくご相談ください。
公式HP
契約書サポート(契約書作成代行、リーガルチェック)
経営管理サポート(バックオフィスを総合的にサポート)
法務財務サポート