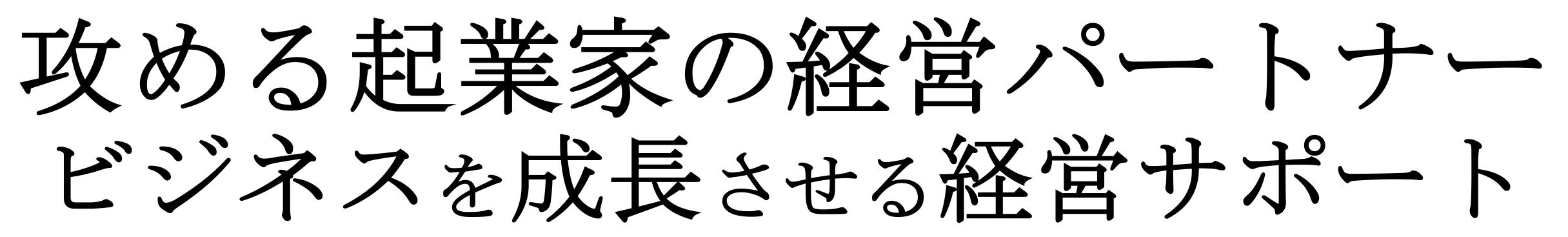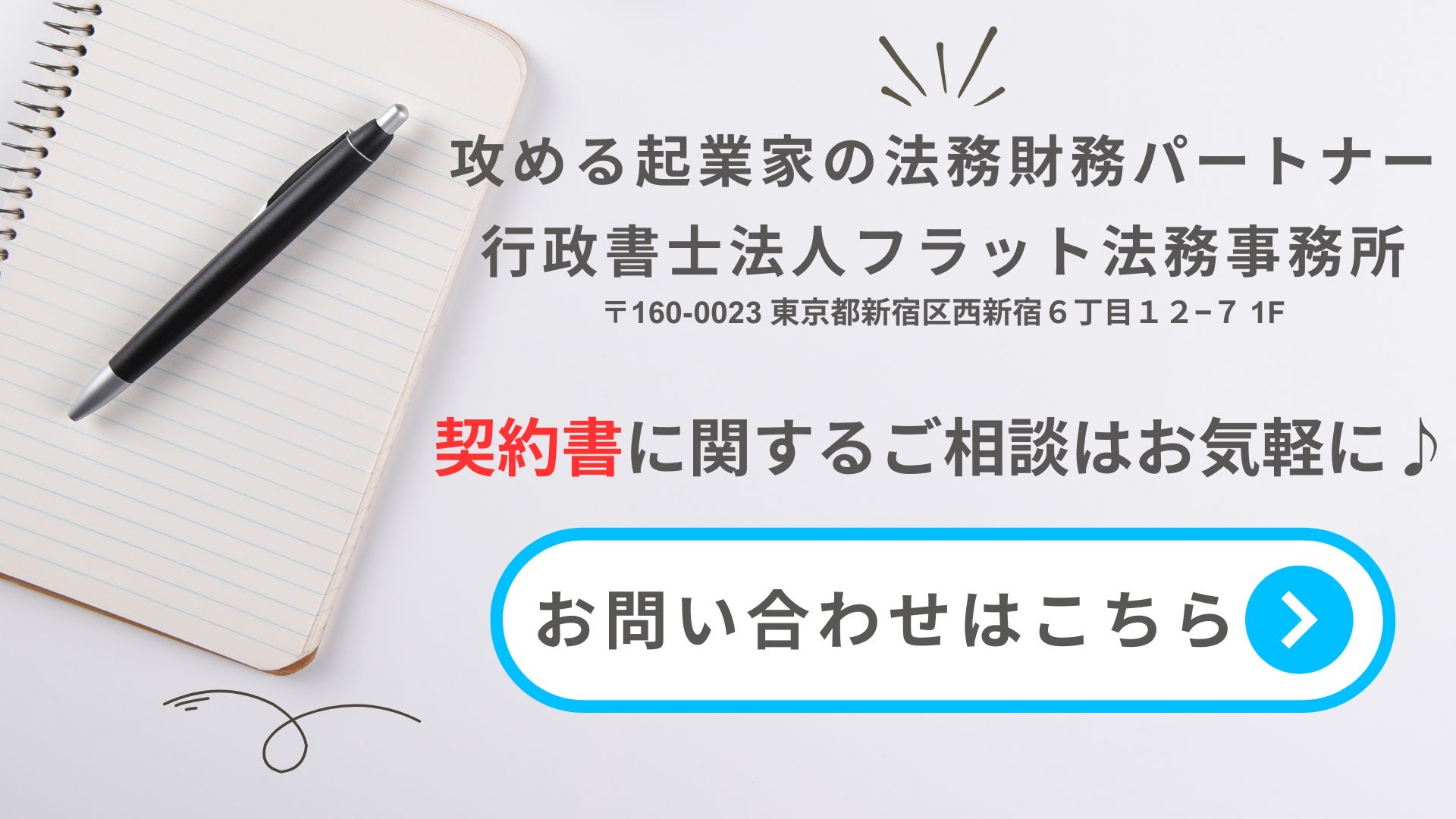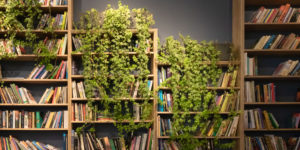製造物責任法と契約書作成:リスク回避のため知っておくこと

製造業や販売業に携わる企業にとって、「製造物責任法」は極めて重要な法律です。この法律は、製品の欠陥によって消費者やユーザーが損害を被った場合、製造者や販売者がその責任を負うことを定めています。特に、消費者保護が強化される現代において、企業は製造物責任に対する対策を講じることが求められます。そこで、企業が製造物責任に適切に対応するために必要な「契約書の作成」について解説します。

1.製造物責任法とは?
まずは「製造物責任法」の基本を確認しましょう。製造物責任法(略称:PL法)は、1994年に施行され、日本国内で製造・販売される製品に欠陥があった場合、その製品が消費者に被害を与えた際に、製造者や輸入業者が損害賠償責任を負うことを定めています。具体的には、以下の3つの欠陥が問題となります。
- 設計上の欠陥:製品の設計自体に問題があり、安全性が確保されていない場合。
- 製造上の欠陥:設計は問題なくても、製造過程でミスがあり、製品が安全でなくなる場合。
- 表示の欠陥:製品の取り扱いや使用方法について不十分な説明があるために事故が発生する場合。
事例:製造物責任法が適用されたケース 具体例として、自動車メーカーの事例を見てみましょう。ある自動車メーカーが製造したブレーキシステムに設計上の欠陥があり、ユーザーが事故を起こしてしまったケースです。この場合、設計ミスによって事故が引き起こされたため、製造者である自動車メーカーはPL法に基づいて損害賠償責任を負いました。このようなケースでは、設計段階での安全対策が不十分であったことが主な問題となります。
2.製造物責任法の適用になる要件
製造物責任法が適用されるには、いくつかの要件が満たされる必要があります。以下の要件が基本的な適用条件です。
- 製造物であること 製造物責任法は「製造物」に対して適用されます。製造物とは、製造された動産を指します。具体的には、一般的に市場で流通している商品や工業製品が該当します。
- 欠陥があること 製品に「欠陥」が存在することが必要です。欠陥には、設計上、製造上、表示上の問題が含まれます。欠陥の概念については後述します。
- 欠陥による損害が発生していること 製造物に欠陥があるだけでは製造物責任法は適用されず、その欠陥によって実際に消費者やユーザーが損害を被った場合に責任が生じます。損害には、生命・身体の損害や、他の財産に与えた損害が含まれます。
- 因果関係の証明 欠陥と損害の間に因果関係があることを立証する必要があります。つまり、製品の欠陥が原因で損害が発生したことを証明する必要があるのです。
これらの要件がすべて満たされた場合に、製造物責任法が適用され、製造者や販売者が賠償責任を負うことになります。
3.製造物の定義
製造物責任法での「製造物」の定義は、製造・加工された動産を指します。動産とは、物理的に移動可能なものであり、製品や部品、消費財などが該当します。例えば、自動車や電気製品、食品、医薬品などが典型的な「製造物」です。
なお、不動産やサービスは製造物責任法の対象外です。たとえば、建築物や土地そのもの、修理やメンテナンスといったサービスは「製造物」には該当しません。また、ソフトウェアのような無形のものも、通常は製造物責任法の適用対象外とされています。
4.欠陥の定義
製造物責任法における「欠陥」は、製品が通常有すべき安全性を欠いている状態を指します。製品の欠陥は大きく3つのカテゴリに分類されます。
- 設計上の欠陥 製品の設計自体が安全でない場合、設計上の欠陥とみなされます。たとえば、製品の設計段階で、重大な安全性の問題が見落とされている場合です。
事例: 自動車のエアバッグが誤作動し、設計上の問題で不適切に展開されてしまうケースがありました。このような事例では、製品の設計が本来の安全基準を満たしていないとされ、設計上の欠陥とされます。
- 製造上の欠陥 設計に問題がなくても、製造過程でのミスや不具合により製品に欠陥が生じることがあります。これを製造上の欠陥と呼びます。たとえば、製造ラインでの管理ミスによって不良品が生産される場合です。
事例: 家電製品である電気ポットの一部が、製造時の誤差により内部でショートしやすい状態になっていたケースでは、製造上の欠陥とされました。
- 表示上の欠陥 製品の使用方法や注意事項に関して不適切な表示や説明が行われていた場合、それが原因で事故が発生したときには、表示上の欠陥が問題となります。具体的には、使用者が安全に使用するために必要な情報が不足している、または誤っている場合です。
事例: ある消費者が薬品を誤った方法で使用して健康被害を受けた場合、その製品の使用説明書に適切な警告や使用方法が記載されていなかったため、表示上の欠陥と判断されました。
5.製造者等の定義
製造物責任法において「製造者等」とは、製造物の欠陥に対して責任を負う主体を指します。具体的には、次のような者が製造者等に該当します。
- 製造業者 製品を実際に製造した企業が、当然に製造物責任を負う主体となります。製造工程を管理し、製品の品質を保証する立場にあるためです。
- 加工業者 製造物を最終的に仕上げるために加工を行った業者も、製造者として責任を負うことがあります。たとえば、部品を組み立てる加工業者などが該当します。
- 販売業者や輸入業者 製品を製造したわけではないが、販売や輸入を行った企業も製造者等に含まれます。特に、海外から輸入された製品については、日本国内の消費者に対して責任を負う輸入業者が製造者としての役割を果たす場合があります。
- 表示業者 自ら製造していなくても、製品に自社名やブランド名を表示している場合、製造者として責任を負うことがあります。これにより、ブランドオーナーも消費者に対する責任を回避することができなくなります。
6.契約書作成時のリスク回避について
製造物責任法に基づいて契約書を作成する際、以下のポイントを盛り込むことでリスクを効果的に回避できます。
1. 責任分担の明確化
製造者、販売者、流通業者の間で、製品の品質や安全性に関する責任を契約書で明確にすることが重要です。これにより、いざ問題が発生した場合の対応をスムーズに行うことができます。
2. 品質保証条項
契約書には、製品が法的に求められる品質基準を満たしていることを保証する条項を盛り込む必要があります。特に、製造過程における品質管理や検査体制についても契約内で言及しておくとよいでしょう。
3. 免責条項の設定
製品の適切な使用方法や安全指示を守らなかった場合、製造者側の責任を限定する免責条項を設定することで、リスクを最小限に抑えることが可能です。
4. 事故発生時の対応体制
製品に欠陥が見つかり、事故が発生した場合の対応体制についても契約書で取り決めておくことが重要です。リコール対応や消費者への連絡手段などを契約で明示しておくと、迅速な対応が可能です。
7.契約書作成時の注意ポイント
契約書を作成する際には、以下の点に注意しておくことが重要です。
1. 法的な専門家との相談
製造物責任に関する契約書は、複雑な法的要素を含んでいるため、必ず弁護士や行政書士などの法的な専門家と相談しながら作成することが推奨されます。法的リスクを最小限に抑えるためには、専門的な視点が不可欠です。
2. グローバルな視点での対応
日本国内のみならず、海外市場にも製品を展開する場合、製造物責任法の適用範囲は国や地域によって異なるため、国際的な法規制にも対応できる契約書を作成する必要があります。特に消費者保護の規制が厳しい地域もあります。国際市場向けの契約書には特に注意が必要です。
3. 契約書の定期的な見直し
製造物責任に関する法制度や判例は、時代とともに変化していくことがあります。そのため、契約書は定期的に見直し、最新の法制度や判例に適応する形で更新していくことが重要です。
8.製造物責任法と契約書の実践的アプローチ
製造物責任法に基づくリスクを軽減するためには、契約書を適切に作成し、企業間での責任分担を明確にすることが重要です。特に、製造者、販売者、流通業者の間でのリスク配分を契約書に明示しておくことで、いざ問題が発生した際に迅速な対応が可能になります。
また、契約書には消費者が製品を正しく使用するための情報提供や、適切な警告を含めることで、製品の欠陥による事故を未然に防ぐことができます。製造物責任法に対応した契約書の作成は、製造業にとってリスク回避の基本となるプロセスであり、適切な法的措置を講じることで、企業はより安心してビジネスを展開できるでしょう。
9.まとめ
製造物責任法に対応する契約書の作成は、製造者や販売者にとって不可欠なリスク管理手段です。品質保証条項や免責条項、適切な情報提供の義務を明示することで、企業は法的リスクを回避し、消費者に安全で信頼性の高い製品を提供することができます。法的な専門家との連携や定期的な契約書の見直しを行うことで、最新の法制度に対応しつつ、企業活動をスムーズに行うことができるでしょう。
*記事内の事例(ケース)については、行政書士法人フラット法務事務所で経験したものだけでなく想定ケースも含まれ、実際の事例とは異なることがあります。また、関係法令は記載した時点のものです。
企業法務や財務等の経営に関することや
契約書の作成やチェックのご相談はお気軽に行政書士法人フラット法務事務所までお問い合わせください♪
行政書士法人フラット法務事務所は、積極的に事業展開している起業家・経営者の皆様に、事業に専念し利益の追求できるようにサポートさせていただき、共にお客様の事業利益の最大化を目指します。
実際にベンチャー企業や中小企業で経営を経験してきたからこそ提案できる企業法務、財務、新規事業の法的調査、融資、出資、経営管理部門サポート等をさせていただきます。個人事業主、一人会社、小さな企業の方もご遠慮なくご相談ください。
公式HP
契約書サポート(契約書作成代行、リーガルチェック)
経営管理サポート(バックオフィスを総合的にサポート)
法務財務サポート