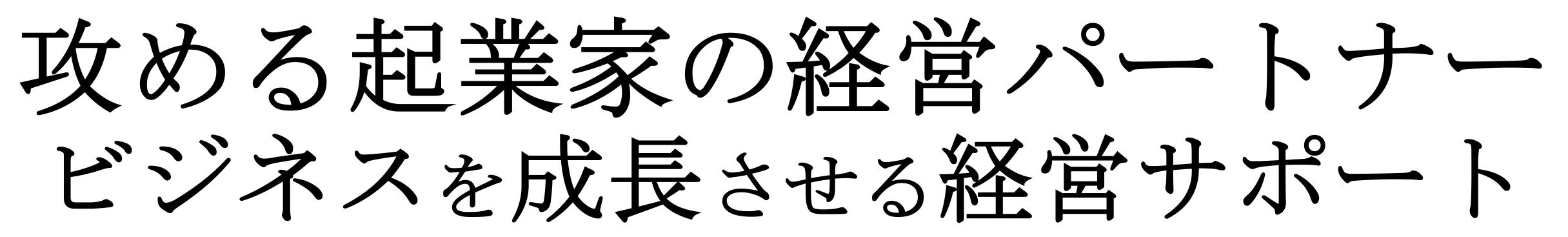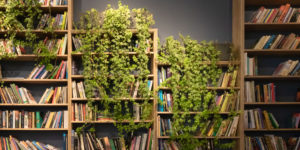土地境界の覚書を活用した不動産取引の安全対策

1. はじめに
不動産取引において、わりと発生するトラブルの一つが「土地の境界」に関するものです。
境界が不明確なまま売買や相続を進めてしまうと、後に隣地所有者と紛争が生じ、訴訟や測量費用の負担といった大きなリスクを抱えることになります。
こうしたトラブルを未然に防ぐ有効な方法の一つが「土地境界に関する覚書」の作成です。
覚書は契約書ほどの厳格さはないものの、当事者間の合意を文書化することで紛争予防の効果を発揮します。
この記事では、土地境界の覚書の位置付けや実務での活用方法、そして実際の事例を交えながら、不動産取引の安全対策としてどのように活用できるのかを解説します。

2. 土地境界の覚書とは?
土地境界の覚書とは、隣接する土地所有者同士が「境界線の位置や取り扱いについて合意した内容」を確認・記録する文書です。
主な内容例
- 境界の位置に関する確認(既存のブロック塀や杭の位置など)
- 将来、測量や建築を行う際の立会い方法
- 境界標の維持・管理に関する合意
- 境界をめぐる費用負担の取り決め
覚書自体は、登記のような効力はありませんが、将来のトラブル防止や合意の証拠として大きな役割を果たします。
3. 境界トラブルの典型例とリスク
覚書がなかったことで起こり得る典型的なトラブルを挙げてみます。
事例① 隣地との塀の位置をめぐる紛争
ある土地の売買後、買主が建物を建築しようとした際、隣地所有者から「その塀は私の土地に越境している」と指摘を受けました。
売主も「昔からある塀だから」と主張しましたが、証拠がなく、最終的には塀を撤去し新設することに。数百万円の費用負担が発生しました。
コメント:売買前に境界の覚書を作成し、塀の所有権や位置を明確にしておけば、こうしたトラブルは回避できたはずです。
事例② 相続後の境界不明確問題
兄弟が相続した土地について、分割協議後に売却を進めようとしたところ、境界が確定しておらず、買主側の金融機関から「境界に関する書面」を求められました。結果として測量・確定作業に半年以上を要し、売却が大幅に遅延。
コメント:相続時には「とりあえず分ける」ではなく、境界の覚書を残しておくことが、後の円滑な売却に直結します。
事例③ 越境物の処理問題
隣地の樹木が敷地に越境していることが発覚し、結局、建築確認が下りなかった。
コメント:覚書で「越境物について将来撤去すること」を合意していれば、建築計画を進める上で安心材料になります。
4. 覚書作成のメリット
土地境界の覚書を作成することには、次のようなメリットがあります。
- 将来の紛争予防
文書化されていれば「言った・言わない」の水かけ論を防げます。 - 売買や融資の円滑化
金融機関や買主に対して、境界に関するリスクヘッジがなされていることを示すことができます。 - 相続時の安心材料
相続人同士の認識齟齬を防ぎ、分割協議をスムーズに進められます。 - 測量費用の削減
将来の境界確定測量がスムーズになり、不要な追加費用を抑制できます。
5. 覚書作成時の注意点
覚書は簡単に作成できる反面、内容が不十分だと後の紛争解決に役立たないこともあります。
注意すべきポイント
- 境界の位置を具体的に記載(できれば図面添付が望ましい)
- 境界標の設置がある場合は、その位置と管理方法を明記
- 今後の工事や測量における立会い方法を取り決め
- 双方が署名押印し、日付を明記
- 必要に応じて第三者(測量士や行政書士)が関与
コメント:覚書は契約書ほどの厳格な内容ではありませんが、公正証書化や実印・印鑑証明を添付すれば、証拠力が格段に高まります。
6. 不動産取引における覚書の活用方法
土地境界に関する覚書は、単に「お互いの合意を確認する文書」にとどまらず、不動産取引の現場ではさまざまな場面で有効に活用されています。ここでは、具体的なケースごとに詳しく見ていきましょう。
6-1.売買契約前の確認
不動産売買においては、境界の確定は極めて重要なチェックポイントです。
売主は「自分の土地がどこまでか」を正確に説明する義務があり、買主も「購入する土地の範囲」を明確に把握しなければなりません。
覚書を事前に作成しておけば、引渡し後に「ここまでが売主の土地ではなかった」という事態を防止できます。特に市街地の住宅地などでは、古いブロック塀やフェンスが境界を曖昧になってしまっているケースもあり、買主からすると将来のリスク要因となります。
事例:ある住宅地で売買契約が進んでいた際、隣地所有者から「塀の一部がこちらの敷地にかかっている」と指摘がありました。急遽、隣地所有者との間で境界覚書を作成し、塀の維持管理と将来撤去について合意することで、取引は予定通り進められました。このように、覚書は取引の円滑化にも直結します。
6-2.金融機関への提出
住宅ローンや事業用融資を受ける場合、金融機関は担保となる土地の境界が明確であるかを重視します。境界に不安があると、融資審査がストップすることも珍しくありません。
このような場合、境界覚書があることで「少なくとも隣接地所有者との間に争いはない」ことを示せるため、金融機関にとってリスクの低減材料となります。特に新築工事を伴う融資では、境界が不明確だと建築確認申請そのものに影響するため、覚書のほか境界の確定測量も必要になってきます。
コメント:実務上、金融機関から境界に関する書類も提出を求められますので、覚書を準備しておくことは資金調達のスピード化にもつながります。
6-3.相続や贈与の際の活用
相続や贈与によって土地が移転する場合、境界をめぐる認識が相続人同士で異なると、後々の分割協議や売却時に大きな支障をきたします。
境界覚書を残しておけば、「父が生前に隣地所有者と境界を確認している」という証拠になり、相続人同士の不要な争いを防ぐことができます。また、将来売却を考える際にも「過去に境界確認がされている土地」として買主からの信頼を得やすくなります。
事例:相続で分割された土地について、後に一部を売却することになったが、境界が不明確だったため測量に時間を要し、買主が離れてしまったケースがありました。生前に覚書を残していれば、もう少しスムーズに取引が進められたと考えられます。
6-4.隣地との共同工事
ブロック塀やフェンス、排水溝の設置・修繕など、隣地と共有する施設の工事を行う際にも覚書は活用されます。工事費用の負担割合や施工位置、維持管理の方法を取り決めておかないと、完成後に「こちらの負担が多い」「塀が境界を越えている」といったトラブルに発展することがあります。
コメント:覚書を交わすことで、双方の合意が明文化され、後日の紛争を未然に防ぐことが可能になります。特に近隣関係は一度こじれると長期にわたるトラブルに発展しやすいため、工事の前段階で合意文書を作成しておくことは非常に重要です。
6-5.開発や建築計画の際
大規模な開発や建築確認を申請する際、隣地所有者からの同意や立会いが必要になります。この場合にも境界覚書があると、「すでに境界について合意している」という前提で手続きを進められるため、境界確定測量をはじめとして、開発許可や建築確認の取得がスムーズになります。
コメント:都市部の狭小地では、わずか数センチの境界のズレが建築計画全体を左右することがあります。覚書があることで設計段階から安心して進められます。
6-6.将来のトラブル解決に備えて
覚書はあくまで「当事者間の確認書」ですが、将来紛争になった場合には有力な証拠として裁判所に提出できます。契約書ほど厳格な内容ではありませんが、当事者の合意が文書で残っているという事実は、解決に向けた大きな材料となります。
コメント:このように、土地境界に関する覚書は、不動産取引のあらゆる局面で役立つ「リスク回避ツール」と言えます。特に売買や融資だけでなく、相続や工事、開発といった幅広い場面で活用できる点が実務上の大きなメリットです。
7. 行政書士が関与するメリット
土地境界の覚書は、当事者だけでも作成可能です。しかし、法律的な裏付けや将来のリスクを見越した条項を加えるには専門家の関与が不可欠です。
- 法的観点からのチェック:曖昧な表現を避け、実効性のある内容に。
- 第三者としての中立性:隣地所有者同士の合意を円滑にサポート。
- 将来のトラブル想定:測量や建築確認など、将来的に起こり得る事態を踏まえた条項を盛り込む。
- 契約書や公正証書との組み合わせ提案:覚書単独では弱い部分を補強できます。
コメント:実務上、境界トラブルの相談を受けた際には「すでに覚書を作っているかどうか」で対応の難易度が大きく変わります。
8. まとめ
土地境界に関する覚書は、不動産取引における「小さな手間で大きな安心」を得られる手段です。
特に売買・相続・共同工事といった場面で活用することで、将来のトラブルを未然に防ぎ、当事者間の信頼関係を維持することができます。
境界問題は「取引成立後に気づくリスク」が多いため、契約前の段階で行政書士などの専門家に相談し、覚書を適切に作成することを強くおすすめします。
*記事内の事例(ケース)については、行政書士法人フラット法務事務所で経験したものだけでなく想定ケースも含まれ、実際の事例とは異なることがあります。また、関係法令は記載した時点のものです。
企業法務や財務等の経営に関することや契約書の作成やチェックのご相談はお気軽に行政書士法人フラット法務事務所までお問い合わせください♪
不動産法務サポート
https://flat-office.com/realestate/
行政書士法人フラット法務事務所は、積極的に事業展開している起業家・経営者の皆様に、事業に専念し利益の追求できるようにサポートさせていただき、共にお客様の事業利益の最大化を目指します。
実際にベンチャー企業や中小企業で経営を経験してきたからこそ提案できる企業法務、財務、新規事業の法的調査、融資、出資、経営管理部門サポート等をさせていただきます。個人事業主、一人会社、小さな企業の方もご遠慮なくご相談ください。
公式HP
契約書サポート(契約書作成代行、リーガルチェック)
経営管理サポート(バックオフィスを総合的にサポート)
法務財務サポート