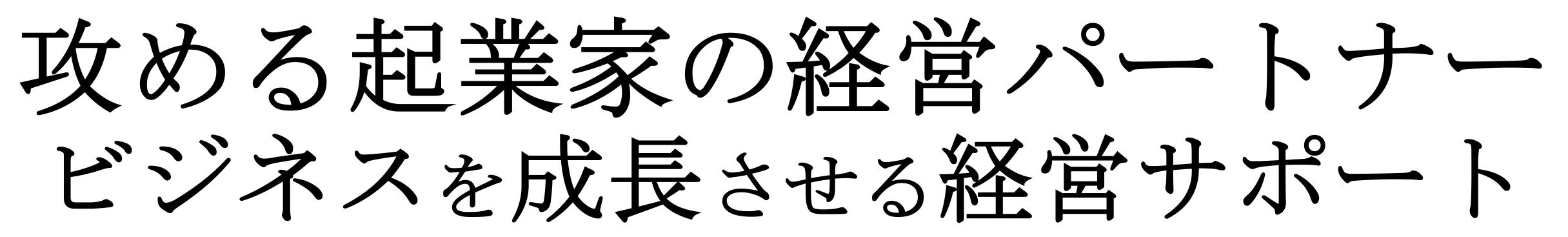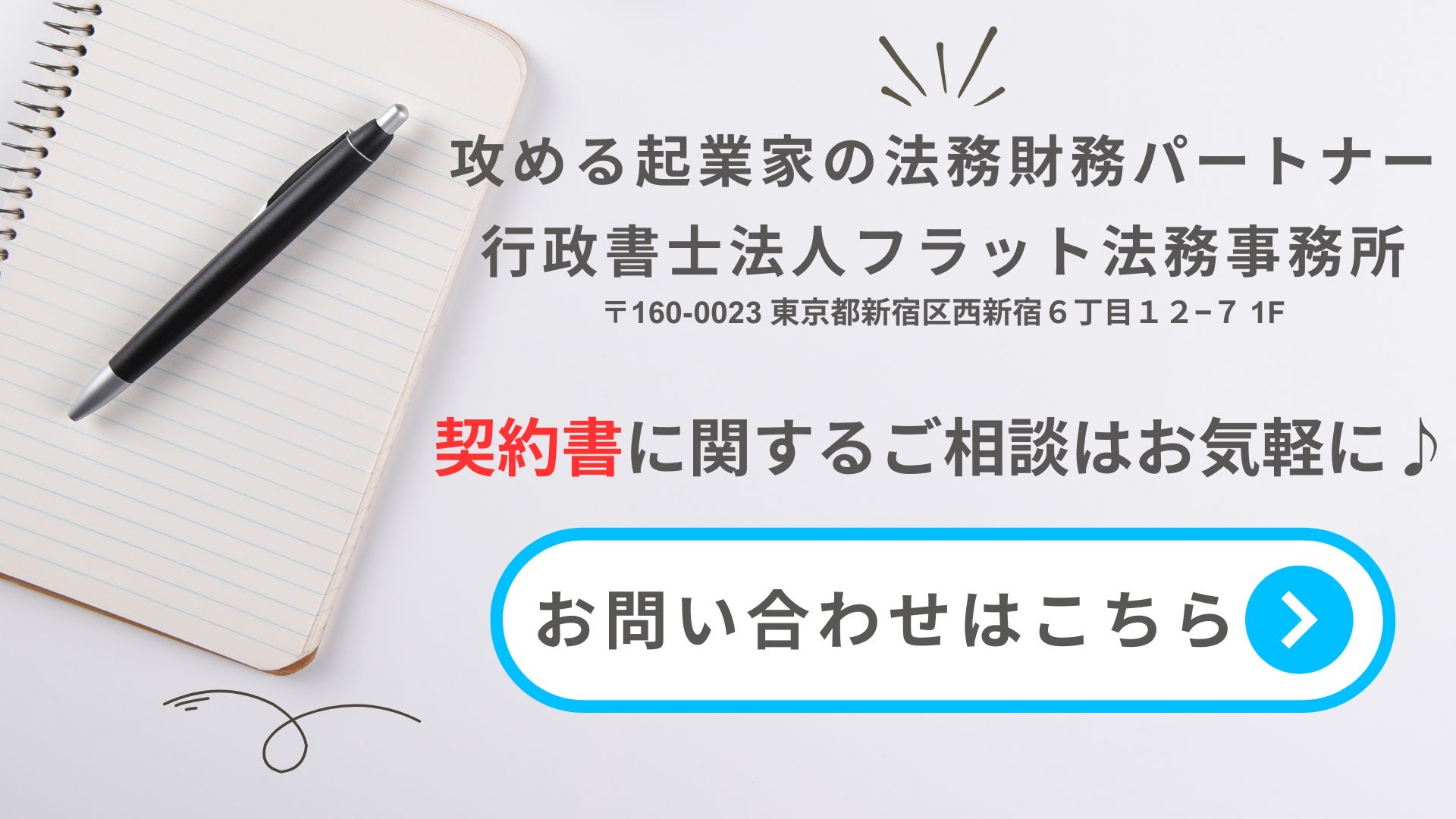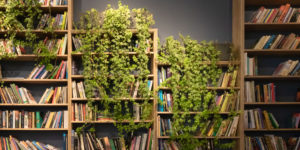連帯保証人の極度額設定とは?契約書に記載すべきポイント

連帯保証人契約は、借主が返済不能となった場合、連帯保証人が代わって債務を履行する責任を負う契約です。特に住宅ローンや事業資金の融資契約、賃貸借契約で頻繁に登場します。この契約には「極度額」という重要な概念が含まれ、連帯保証人の責任範囲を明確にするために設定されます。本記事では、連帯保証人契約における極度額の重要性、契約書にどのように記載すべきか、そして具体的な事例と共に解説していきます。また、契約書における連帯保証人の極度額設定についても詳しく触れます。

1. 連帯保証人とは?
連帯保証人は、債務者(借主)が債務を履行できない場合に、債権者に対して同等の責任を負う人物です。通常の保証人とは異なり、連帯保証人は債務者が履行を怠った時点で即座に支払い義務を負うことになり、債権者から直接請求を受けます。そのため、連帯保証人になることは非常にリスクが高い行為です。
事例1:親が子供の住宅ローンの連帯保証人になるケース 例えば、親が子供の住宅ローンの連帯保証人となった場合、子供がローンを返済できなくなった時点で、親が全額を支払う義務を負うことになります。このリスクを軽減するために重要なのが、極度額の設定です。
2. 極度額とは?
極度額とは、連帯保証人が負担する債務の上限額を明示するものです。極度額を設定することで、保証人が無制限に債務を負うリスクを回避できます。
法的背景 日本では、2017年の民法改正により、連帯保証契約には極度額を明記することが義務化されました。極度額が設定されていない連帯保証契約は無効とされるため、この設定は非常に重要です。これは、保証人の過大な負担を防ぐための措置です。
事例2:事業融資における極度額設定のケース 事業融資で、代表取締役が会社の融資に対して連帯保証人になる場合があります。この際、極度額を設定しないと連帯保証契約は無効とされます。極度額を明示し適正な範囲内であれば、例えば「〇〇円まで」といった形で代表取締役の負担を制限できます。
3. 法人と個人が連帯保証人になる場合の違い
連帯保証人には、個人だけでなく法人がなるケースもあります。法人と個人では、責任の範囲やリスクが異なるため、それぞれの違いを理解することが重要です。
3.1 法人が連帯保証人になる場合
法人が連帯保証人になる場合、会社の資産や財務力が重要な要素となります。法人は、個人よりも通常多くの資産や収入を持つため、債権者にとっては信頼性の高い保証人となります。そのため、極度額の設定も必要ありません。
例えば、子会社の融資に対して親会社が連帯保証人となる場合、親会社の財務力が強ければ極度額をなくすことで、より大きな責任を負わせることが可能です。
3.2 個人が連帯保証人になる場合
一方、個人が連帯保証人になる場合、個人の資産や収入には限界があります。個人の極度額は、一般的に財務状況に応じて適切な範囲に設定されるべきです。無理な額を設定すると、連帯保証人が支払い不能に陥り、さらなるトラブルを引き起こす可能性があります。また、個人が連帯保証人の場合には、事業性融資で、さらにその事業に関係が深くない者が連帯保証人になるケースでは、公証役場で保証意思確認のための公正証書が必要となります。
事例3:法人 vs 個人の連帯保証人の違い ある中小企業が銀行から融資を受ける際、経営者個人が連帯保証人になるケースが多くあります。個人の財務力が限定的であるため、極度額もある程度制限されることがあります。一方で、同じ融資に対して親会社が連帯保証人となる場合、極度額は設定されないか高額に設定されることがあり、法人としての保証力が評価されます。また、ケースによっては公証役場での手続きが必要になります。
4. 賃貸借契約における連帯保証人の極度額
賃貸借契約では、家主(貸主)が借主に対して賃料や修繕費などの債務履行を保証するために、連帯保証人を立てるケースが一般的です。この際にも極度額の設定は必須(個人保証の場合)であり、家主や保証会社とのトラブルを防ぐ役割を果たします。
4.1 賃貸借契約における極度額設定の意義
賃貸借契約では、賃料や修繕費、不払いや損害賠償など、債務が多岐にわたるため、連帯保証人にとって負担が大きくなるリスクがあります。そのため、極度額を設定することで、保証人が支払わなければならない金額に上限を設けることができます。
4.2 賃貸借契約書の極度額記載例
賃貸借契約書に極度額を記載する場合、賃料や修繕費などの債務全体に対する保証の上限を設定することで、保証人の責任範囲が明確になり、トラブルを避けることが可能です。
事例4:賃貸物件での連帯保証人トラブル 民法改正以前では、ある賃貸物件で、借主が数ヶ月分の賃料を滞納し、その後部屋の修繕が必要になりました。連帯保証人には極度額が設定されておらず、全額を負担することになり、予想以上の出費に苦しむことになりました。このような事態は、極度額を設定していれば避けられるものでした。
5. 極度額設定のメリットとリスク回避策
5.1 連帯保証人の保護
極度額を設定することで、連帯保証人は無限責任を負わず、リスクを限定できます。特に友人や親族間での保証契約において、信頼関係を保ちながら、責任を明確にしてトラブルを防ぐことが重要です。
事例5:親族間での賃貸借契約における保証契約 あるケースでは、親が子供の賃貸借契約に連帯保証人となりましたが、極度額を設定しておらず、子供が賃料を滞納した際に予想外の負担を強いられることになりました。このような親族間の契約では、極度額の設定が特に重要です。(民法改正以前)
5.2 債権者の保護
極度額の設定は、連帯保証人だけでなく、債権者(家主や貸主)にとってもメリットがあります。極度額が設定されていることで、保証人に対して過剰な請求をするリスクがなくなり、法的トラブルを未然に防ぐことができます。
5.3 極度額設定によるトラブル防止
極度額を契約書に明確に記載することで、万が一の際の法的トラブルを避けることが可能です。賃貸借契約でも、極度額が明示されていれば、保証人の負担額が明確になり、交渉や訴訟がスムーズに進みます。
6. 極度額設定に関する最新の法的動向
連帯保証契約に関しては、法改正や判例の影響を受けることが多いため、契約書の内容を定期的に見直すことが推奨されます。特に賃貸借契約においては、法律や判例が保証人の負担を軽減する方向に進む傾向があります。
事例6:賃貸借契約における法改正の影響 最近の法改正により、賃貸借契約における連帯保証人の極度額が明確に義務付けられました。この改正に基づいて、極度額を見直した賃貸契約書を作成することで、家主と保証人の双方が安心して契約を結ぶことができるようになりました。
7. まとめ
連帯保証人契約における極度額の設定は、住宅ローンや事業融資だけでなく、賃貸借契約においても非常に重要です。極度額を設定し、契約書に正確に記載することで、連帯保証人の負担を限定し、トラブルを防ぐことができます。また、法的な知識や最新の動向を踏まえて、契約内容を適切に更新することが必要です。
契約書へ記載の極度額設定や、連帯保証人の契約について疑問や不安がある場合は、ぜひ専門家に相談し、適切なサポートを受けることをお勧めいたします。
*記事内の事例(ケース)については、行政書士法人フラット法務事務所で経験したものだけでなく想定ケースも含まれ、実際の事例とは異なることがあります。また、関係法令は記載した時点のものです。
企業法務や財務等の経営に関することや
契約書の作成やチェックのご相談はお気軽に行政書士法人フラット法務事務所までお問い合わせください♪
行政書士法人フラット法務事務所は、積極的に事業展開している起業家・経営者の皆様に、事業に専念し利益の追求できるようにサポートさせていただき、共にお客様の事業利益の最大化を目指します。
実際にベンチャー企業や中小企業で経営を経験してきたからこそ提案できる企業法務、財務、新規事業の法的調査、融資、出資、経営管理部門サポート等をさせていただきます。個人事業主、一人会社、小さな企業の方もご遠慮なくご相談ください。
公式HP
契約書サポート(契約書作成代行、リーガルチェック)
経営管理サポート(バックオフィスを総合的にサポート)
法務財務サポート