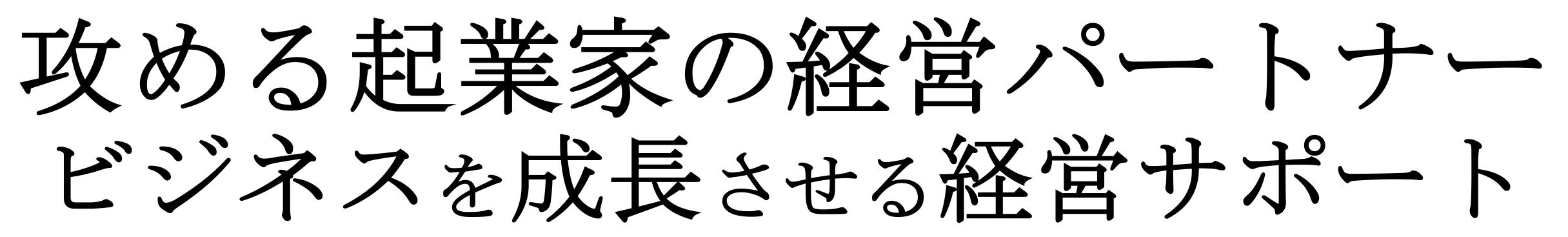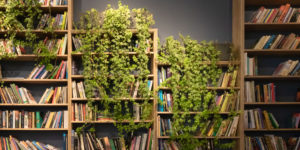宅建業者売主の契約で手付金解除はいつまで可能?実務でのポイント解説


1. はじめに
不動産売買契約において「手付金解除」という制度は、契約当事者が契約を解約できる重要な制度です。
宅建業者が売主の場合、宅建業法による規制が適用されるため、個人売主との契約とは異なる点があります。特に注意すべきは 「手付金解除がいつまで可能なのか」 という点です。
不動産取引の現場では、買主はいつまでなら解除できるのか、売主はどのタイミングで契約の安定を図れるのか、という点でトラブルが生じやすいです。
本記事では、宅建業者売主の契約における手付金解除の実務ポイントを、条文や判例、具体的な事例を交えて解説します。
2. 手付金解除の基本ルール(民法)
民法における手付金解除の基本は以下の通りです。
- 手付金は「解約手付」と推定される(民法557条1項)
- 手付金解除は、相手方が履行に着手するまで可能
- 買主は手付金を放棄することで契約を解除できる
- 売主は手付金の倍額を返すことで契約を解除できる
つまり、履行に着手するまでは、契約当事者は手付金を使って契約を解除することが可能です。
履行の着手とは、売主が登記申請や代金受領など、実際に契約履行の行為に入ったことを指します。
3. 宅建業法による特則:宅建業者売主の場合
宅建業者売主の場合、宅建業法が適用され、買主保護のために以下の点が定められています。
3-1. 手付金額の制限
宅建業者が受け取る手付金は、売買代金の2割を超えてはいけません。これは買主が高額な手付金を一度に支払うことで、契約解除が困難にならないようにするためです。
3-2. 手付金解除権の保護
宅建業法39条は、民法の手付解除権を買主に保障する趣旨も持っています。
- 買主は、売主が契約履行に着手するまでは、手付金を放棄して契約を解除できます
- 契約書で不当に解除権を制限する条項は、宅建業法や消費者契約法などの観点から無効となる場合があります
また、宅建業法には「契約締結から◯日間解除可能」という固定の期間は規定されていません。
4. 個人売主の場合の手付解除
個人売主(宅建業者でない売主)の場合は、民法がそのまま適用されます。
4-1. 基本ルール
- 手付解除は、履行に着手するまでとしても可能
- 契約書で解除期限を設けることも可能(例えば「契約後7日以内に解除できる」など)
- ただし、解除権の制限が不当と評価される場合は無効になることもある
4-2. 実務上の注意
- 個人売主は慣れていないことが多く、解除条件の認識が曖昧になる場合がある
- 買主は契約書の文言と民法上の解除権の関係を確認する必要がある
- 履行着手の定義を明確にしておかないと、トラブルに発展しやすい
5. 宅建業者同士の取引
宅建業者同士の不動産取引では、民法・宅建業法の両方を考慮しながらある程度自由に適用できます。
5-1. 手付金の取り扱い
- 本来は、手付金の額は売買代金の2割を超えてはならない
- 契約書で解除条項を設定することも可能だが、当事者が宅建業者同士の場合、買主は通常業務の一環としてリスクを理解しているため、条項の自由度は比較的高い
5-2. 実務上の注意
- 手付解除の判断は個人相手よりも柔軟で、登記手続きや決済の進行状況で解除権が制限される
- 取引慣行として、契約締結後すぐに手付解除が行使されることはほとんどなく、むしろ契約履行を前提とした交渉が中心
6. 実務でのポイント:いつまで解除できるのか
宅建業者売主との契約では、手付金解除が可能か否かは 「履行に着手したかどうか」 が最大のポイントです。下記の事例はあくまで目安です。実際に紛争になった場合には、裁判所によって個別に判断されます。
事例1:買主が住宅ローン審査中
- ローン審査を受けている段階では、履行の着手にはあたりません
- したがって、手付金解除は可能です
事例2:売主が登記申請書類を作成した段階
- 書類作成だけでは履行の着手とは評価されません
- この段階でも解除可能です
事例3:買主が残代金の一部を支払った場合
- この時点で履行の着手と評価されることが多く、解除はできなくなります
7. トラブル事例と実務コメント
事例A:契約直後に買主が解除を申し出たケース
- 売主は「契約当日に履行に着手した」と主張
- 実際には書類準備のみであったため、裁判所は買主の手付解除を認めた
コメント:宅建業者側は契約の安定を図りたいが、履行着手の判断は慎重に行う必要があります
事例B:引渡し直前に解除希望
- 買主は「まだ履行着手していない」と主張
- 売主は残代金の一部受領済みであったため、解除は無効
コメント:履行の着手が解除可能か否かの争点になることが多い
事例C:契約書に解除制限条項があったケース
- 契約書に「契約後5日以内は解除できない」との条項
- これは民法・宅建業法の趣旨に反すると判断され、無効
コメント:契約書の不利な特約は、消費者保護の観点からも無効とされる可能性がある
8. まとめ
- 宅建業者売主の契約では、手付金の上限は売買代金の2割まで
- 買主は、契約履行に着手するまで手付金を放棄して契約解除可能
- 「契約から10日間保証」といった法定規定は存在しない
- 履行に着手したか否かが実務上の最大の争点
- 契約書に解除条項を設ける場合は、民法・宅建業法の趣旨に沿って具体的に記載する
- 個人売主の場合は民法が原則
- 宅建業者売主は宅建業法39条の制限に注意
- 宅建業者同士は、条項自由度が高いものの履行着手の判断が重要
不動産売買は高額取引であり、手付解除の権利を正しく理解することが、買主・売主双方にとっての安心につながります。
| 売主の種類 | 手付解除の可否 | 注意点 |
| 個人売主 | 履行に着手するまでとすることも解除期限を設けることも可能 | 契約書に解除期限を設ける場合は民法準拠 |
| 宅建業者売主 | 履行に着手するまで | 手付金は2割上限。解除権の制限条項は無効 |
| 宅建業者同士 | 履行に着手するまで原則 | 実務慣行として解除権は制限されやすい。契約書で明確化を推奨 |
*記事内の事例(ケース)については、行政書士法人フラット法務事務所で経験したものだけでなく想定ケースも含まれ、実際の事例とは異なることがあります。また、関係法令は記載した時点のものです。
企業法務や財務等の経営に関することや契約書の作成やチェックのご相談はお気軽に行政書士法人フラット法務事務所までお問い合わせください♪
不動産法務サポート

行政書士法人フラット法務事務所は、積極的に事業展開している起業家・経営者の皆様に、事業に専念し利益の追求できるようにサポートさせていただき、共にお客様の事業利益の最大化を目指します。
実際にベンチャー企業や中小企業で経営を経験してきたからこそ提案できる企業法務、財務、新規事業の法的調査、融資、出資、経営管理部門サポート等をさせていただきます。個人事業主、一人会社、小さな企業の方もご遠慮なくご相談ください。
公式HP
契約書サポート(契約書作成代行、リーガルチェック)
経営管理サポート(バックオフィスを総合的にサポート)
法務財務サポート